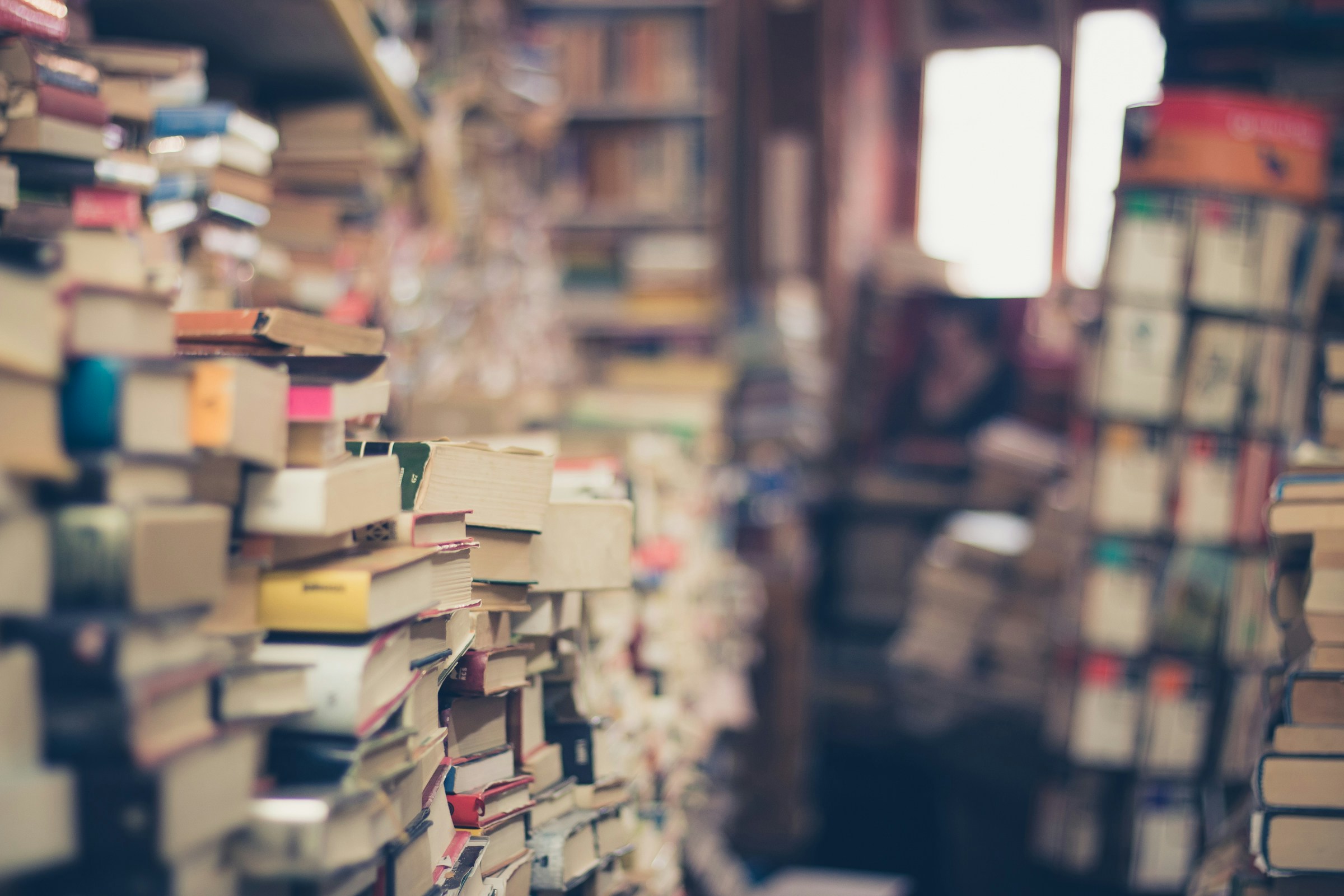こんにちは。ノムです。
今回は宅地建物取引士の合格までの道のりを紹介します。
ノムは4回目で合格しました。落ちすぎ...
この記事を読んでわかる事
・勉強スケジュール
・合格に至るまでに失敗した事や気付いた事、やってよかった事など紹介
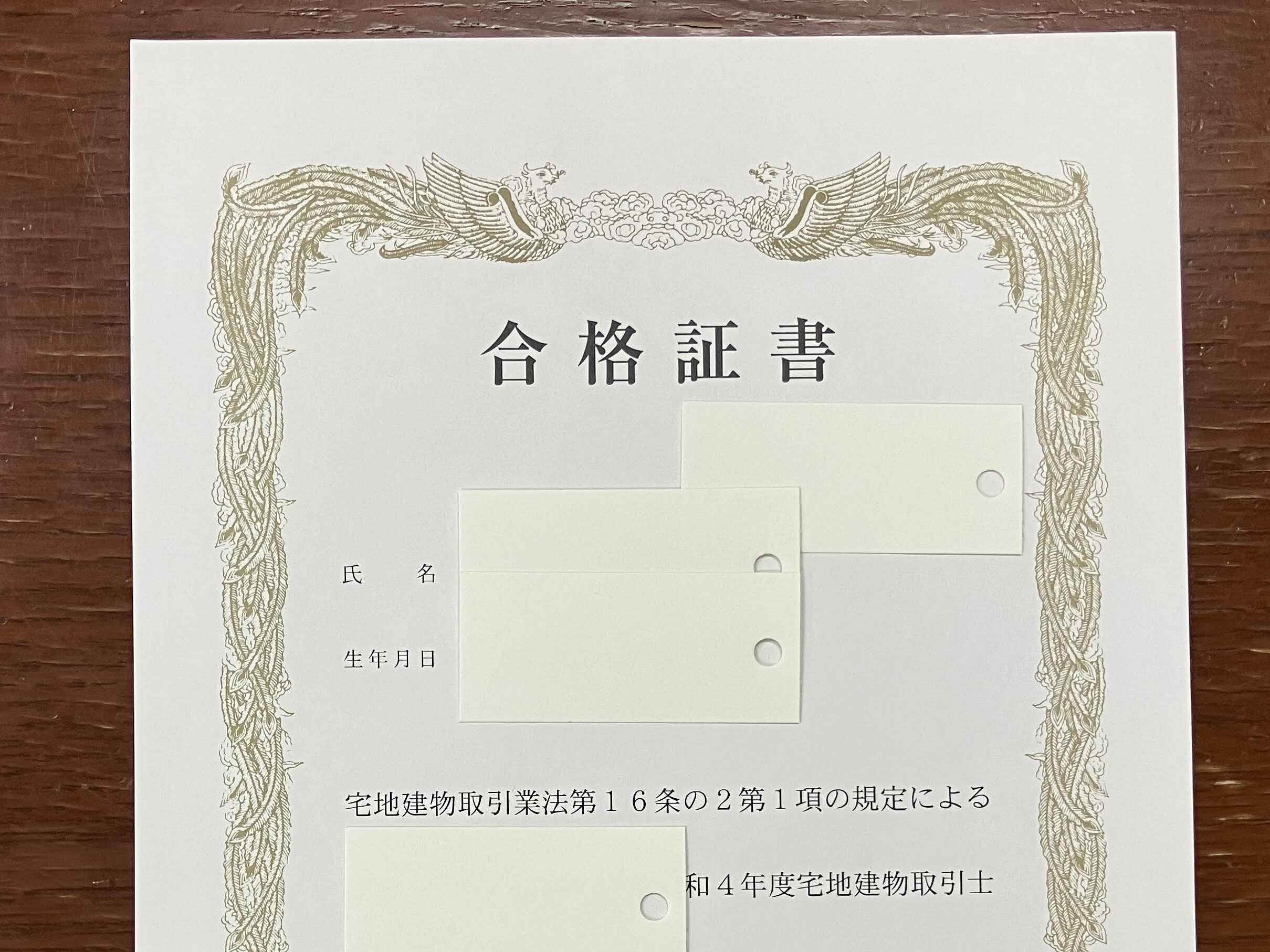
ノムは試験に3回連続で落ちています。4年目でやっと合格。

最初からもっとまじめに勉強すればよかった...
さて本題の合格までに4年間の勉強を通して失敗した事気付いた事など紹介していきます。
読んでいて当たり前な事だと感じるかもしれませんが、どうぞお付き合いください(__)
ノムが合格できた年の勉強スケジュール
失敗例を紹介する前に...
試験は10月で7か月前の3月から勉強しました。
3月~6月:教科書と1問1答問題集で基礎固め
テーマ毎の大枠を理解していく作業。1問1答で間違えた問題は繰り返し復習。
全範囲をとにかく早く掴んで教科書ベースの勉強を終わらせます。

ここで時間をかけすぎない
6月から8月:テーマ別の過去問題集で全範囲2週目の勉強
教科書の範囲を1周終えた所で教科書ベースから過去問題集で勉強
3つの意味があります。
- 基礎から演習問題で曖昧な理解から精度の高い理解を深める
- 不得意なテーマを知る
- 試験に近い4択で答えを導き出す練習
特に過去問題集を解くという意味では
1周目、1問1答で勉強しているので同じでは?と思うかもしれません。
しかし、
1問1答では〇×形式です。
過去問題集を使う事で試験に近い4択で答えを導き出す練習が効果的だと思います。

100%暗記は現実的ではないですからね。4択で推測する力を付けます。
間違えた問題は正解するまで繰り返し解きます。
ノムはよく理解の仕方が間違って覚えていて正解できない問題が多かったです。

理解力なぁです。
9月から10月(試験当日):過去問10年分を取り組む
ノム的にはここが一番重要な作業だと思います。
2つの意味
- とにかく苦手な所を無くしていく作業。
- これ答えれへんやろ!応用問題に触れておく作業
過去問によっては解説で正答率を表記付けてくれる物もあります。
例えば:正答率、A、B、C、の3段階あるとすればAは絶対落としてはいけないという事です。
ライバルと差をつけるのはB、C問題という事です。
試験範囲としては4つのテーマで50問です。
民法等(権利関係):14問
・宅建業法:20問
・法令上の制限:8問
・税・その他:8問
合格点は変動しますが、35点前後です。

ノム的には民法が難しく感じるので、業法でカバーです。
合格した年のスケジュールはこんな感じでした。
では3年間落ち続けて何をしていたのか?
3年間の失敗と気づいた事など紹介します。
5つの失敗・反省
- 受験日まで逆算せずに勉強スケジュールを立てていた
- 1問1答の問題集ばかり解いていた
- 苦手な項目をしっかり分析せずにただ過去問を解き続けていた
- 模試を受けていなかった
- 過去問を数年分しかやらなかった
以上が失敗した事だと考えています。
一つずつ解説します。
失敗1.受験日まで逆算せずに勉強スケジュールを立てていた。
→試験では4つカテゴリーがあります。権利関係、法令上の制限、宅建業法、税・その他、です。
試験合格に必要な勉強時間は、300~500時間程度と言われます。
限られた時間にどう勉強時間を割り当てるか
教科書通りに勉強すれば権利関係から取り組む事になりますが、
え、業法から?

個人的には権利関係は難しいと感じます。
聞きなれない法律用語があったりで理解するのに時間を取られるんですよね...
しかも宅建が嫌になる。
スタートいきなり挫折したらモチベーション駄々下がりです。

ノムの場合:理解しようとずっと民法に時間を当ててしまいました。
時間を決めずダラダラと勉強。
だから試験日までに勉強が間に合ってないんやな。当たり前だよなぁ
仕事、学業、取り組み始めた時期など人によって時間が変わってきます。
10月までの時間を見て、しっかり自分基準で1日に確保できる勉強時間、しなければいけない時間を導き出してスケジュールを立てましょう。
失敗2. 1問1答の問題集ばかり解いていた
1問1答問題集は教科書のテーマごとに学んだ後、
軽く理解度チェックの為に、活用すべきだったと思いました。
というのは
1問1答を満点が取れるまで何度も解き直す事で
そのテーマはしっかり理解できたと勘違い
実際、過去問を解いてみると論点は一緒ですが問われ方が違っていたりと1問1答ではカバーしにくい所がありました。
しかも単に〇×形式なので、実際の4択となると…
失敗3. 苦手な項目をしっかり分析せずにただ過去問を解き続けていた
例えば、ノムの場合
保証金制度が苦手でした。
したがって、保証金制度のテーマの過去問を解いていく作業でした。
ではなくて、
保証金制度の中で、営業保証金の供託と保証協会の加入の違いでごっちゃになっている。
と一歩踏み込んだ分析がしっかりできていない所がありました。

全部してたらキリがないので毎回間違える問題のテーマで見直すのがおすすめ
失敗4. 模試を受けていなかった
模試を受けなかった理由として、過去問を自宅で解けばいいのでは?
と考え受けていませんでした。
しかし、模試を受ける事で得られるものがありました。
会場での試験を受ける緊張感、問題を解く時間配分、マーク式の解答方法、、、
解答時間がギリギリまでかかってしまう。

自宅だと試験時間が余るのに、、、
など
実際に試験を受ける雰囲気をなんとなく感じる事ができてよかったと思いました。
失敗5. 過去問を数年分しかやらなかった
3年か5年分しかやっていませんでした。
理由は、試験日まで勉強が間に合わなかった事、1年分を満点が取れるくらいまでしっかり解き直す事を優先していた事が理由です。
それを10年分やろう。

要は、そもそも行動量が足りていない
過去問を解き始める事が宅建の勉強で一番大事な事なので、、
まとめ
合格できた年のスケジュール
- 3月~6月:教科書と1問1答問題集で基礎固め
- 6月から8月:テーマ別の過去問題集で全範囲2週目の勉強
- 9月から10月(試験当日):過去問10年分を取り組む
5つの失敗・気付いた事
- 受験日まで逆算せずに勉強スケジュールを立てていた
- 1問1答の問題集ばかり解いていた
- 苦手な項目をしっかり分析せずにただ過去問を解き続けていた
- 模試を受けていなかった
- 過去問を数年分しかやらなかった
以上、5つが4年間の勉強を通して分かった失敗・気付いた事です。
人によって勉強方法は様々ですが、私はこんな感じでした。
おまけ
2025年度に不動産賃貸経営管理士の試験に挑戦します。
こんな偉そうに宅建の勉強記事を書かせてもらってますが、全くというわけではありませんが、勉強そんなに進んでません。

口で言うのは簡単という事ですね(-_-;)
包み隠さず、合否も公開していきたと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。